こんにちはーー
古事記子供シリーズ第3弾まで読み込み動画をアップしていましたが、
やっと、第4弾ができましたー。
「やまたのおろち」です。
もちろん、かわいい絵カード紙芝居は、Supermom Japan のものを使わせていただきました!!
さてさて、、
大蛇を退治したスサノオは、
「その根は、根の国に岩根に届くほど深く広がり、その枝は、神々の住む空の果てに届くほど高くそびえよ。その葉は、玉はがねのかがやくごとくかがやけ。」
といって自分のひげをぬいてかぜにさらしたら、ひげから、胸毛から眉の毛からぐいぐいいろいろな木生えて、根はしっかりと地の奥深くに根づいたそうです。
そして、その木でできた御殿を、スサノオが気に入った土地、出雲に建てて、歌を詠んだのですね。
「八雲立つ 出雲八重垣 妻ごみに 八重垣つくる その八重垣を」
(群がり重なりあって立つ雲、出雲の国に垣根のように立つ雲よ、愛する私の妻と私の暮らしを包み込むようにして立ち上る雲よ、垣根のような雲よ」
有名な歌ですね。。

クシナダ媛は、稲田を守り、スサノオは砂鉄を取って玉鋼(たまはがね)を人々に作らせたといいます。そして、作っているときにも、稲田を守るために、稲に水を引く間は人々に、この仕事をやめさせて、使った木は次々に飢えさせたために、肥の川の水は玉のように澄み、木は青々と生い茂ってそれはそれは美しい所だったそうです。
巨大なへび、八岐大蛇の正体は???
八岐大蛇なんて、、そんな蛇がいたのか?・っておもますよね。
実は、やまたのおろちは、川という説があり、洪水をあらわしているというのです。
そういえばそうですね、、太くて、くねくねうねり、暴虐の限りを尽くす、、、というのが、川が氾濫して洪水になった時のことと似ているかもしれません。
ところで、、、
皆さんは、さまざまな神話の場面をお芝居のようにしてみせる、「神楽」という伝統芸能があるのを知っていますか?
島根県の「石見神楽」
室町時代の後期にはじまったといわれる、収穫期に自然や神さまに感謝を表す神楽の儀式で、もともとは、神職による儀式だったそうです。それが、だんだんと、民間の大衆芸能として発達していったんですね。
この動画では、秋祭りの夜9時から明け方まで行う「奉納神楽」についてみることができます。そして、最後の方19分あたりで、「八岐大蛇」の演目が始まるのですが、それがすごくてすごくて!!!!
ぜひ、ぜひぜひーーーー見てください!!!
日本の伝統芸能は、歌舞伎、能、狂言、人形浄瑠璃、などなどたくさんありますが、いっやー、、、
奥深いですねーーーー。日本。。。
それではまた!!
Learn Japanの歴史教室は、まだまだ生徒さまを募集しています。
途中参加大歓迎の、4週間無料体験実地中なので、どうぞふるってご参加くださいませ。
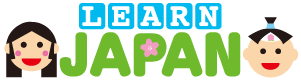





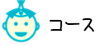




コメント